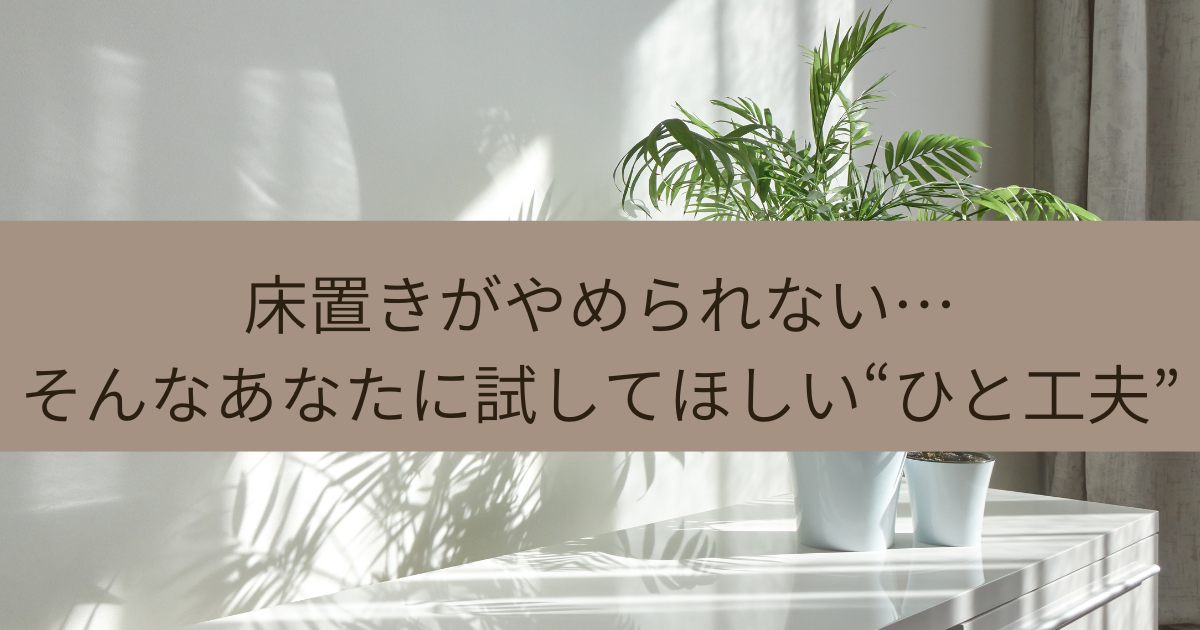気づけばリビングの隅や玄関に、ついポンと物を置いてしまう。
そのまま置きっぱなしになって、片付いていない印象に…。
そんな「床置きグセ」、実はかなり多くの人が抱える悩みです。
でも、それを無理にやめようとする必要はありません。
この記事では、床置きをゼロにするのではなく、
“床置きしてしまう場所”に合わせて「仕組み」をつくるという視点で、
暮らしがラクになる工夫をご紹介します。
「片付け=我慢」ではなく、「片付け=仕組み」と考えてみませんか?^^
前提:床置きは“悪”じゃない
SNSや雑誌で見るすっきりした部屋に憧れて、
「床置きはダメ」「モノはすべて収納へ!」と思いがちですが、
実際の暮らしでは、いつも完璧にするのは難しいですよね。
私自身も昔は「帰ってきたらカバンは床に直置き」
「読みかけの本は机に置いたまま」…なんて毎日でした。
でもそれって、ある意味“暮らしに合ってる動線”だったんです。
だから、「床置きしてしまう自分を責める」のではなく、
「床置きしたくなる場所に“受け皿”をつくる」ことで、
自然と整った空間に近づいていくことに気づきました。
次はその具体的な工夫を紹介していきます!
工夫①:よく床置きする場所に“かご”を置く
これは、私が一番最初に取り入れて効果を感じた方法です。
カバンを床に置いてしまう場所に、100均のかごを1つ置くだけ。
それだけで、床置きが“定位置”に早変わり。
「ここに置いてOK」と自分に許可を出すような気持ちで、
まずは“仮の居場所”を作ってあげることが大事です。
ポイントは、「見える場所に置いても生活感が出にくい素材を選ぶ」こと。
ナチュラルなかごや布素材のボックスなら、インテリアにもなじみやすいですよ◎
工夫②:一時置きの“理由”を知っておく
モノを置きっぱなしにしてしまう背景には、
「あとでまた使うから」「今はしまう時間がないから」といった理由があります。
この“理由”をちゃんと把握しておくと、
仕組みをつくる時に無理がなくなります。
例えば、
- 帰宅後すぐカバンを置きたい → 玄関やソファ横に定位置を
- 読みかけの本をすぐ取りたい → リビングの一角にマガジンラックを
一時置きしたくなる動線に合わせて、
「置いても散らからない場所」をあらかじめ用意しておくことがポイントです。
工夫③:一度“空のBOX”を置いてみる
これ、実は片付けの習慣づけにもなるんですが、
あえて最初から「空のBOX」をポンと置いておくんです。
すると、何かを置きたくなったときに、
自然とそこに入れるようになります。
視覚的にも、BOXにおさまっていると「片付いてる感」が出やすく、
無理なく習慣化しやすいんです。
私はこの方法で、「床に広がっていたものが自然とまとまる」
という快感を覚えたことで、床置きの量がどんどん減っていきました^^
まとめ:片付けは“やめる”より“整える”
床置きをゼロにしようとがんばるより、
「どうせ置くなら整えて見せよう」と思った方が、
片付けはずっと気楽になります。
毎日使うものこそ、“しまいすぎない仕組み”が必要。
まずは、床置きが起きがちな場所にかごを1つ置いてみることから始めてみてください^^
暮らしは、ちょっとした工夫でぐっとラクになりますよ🌿